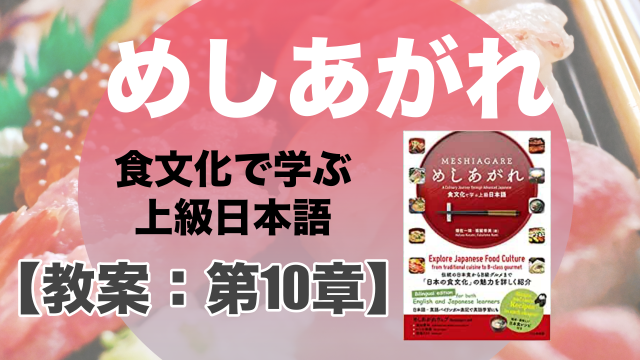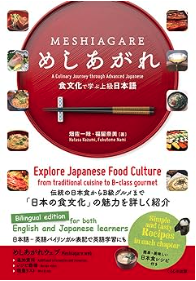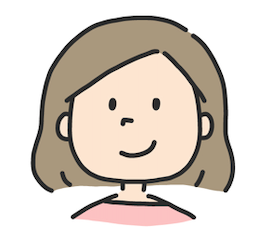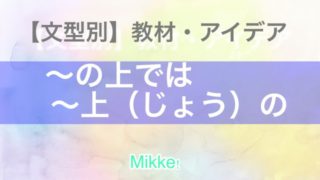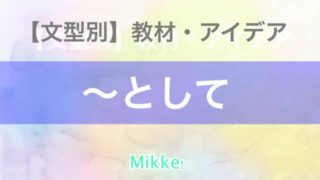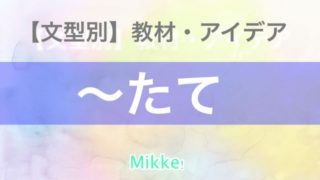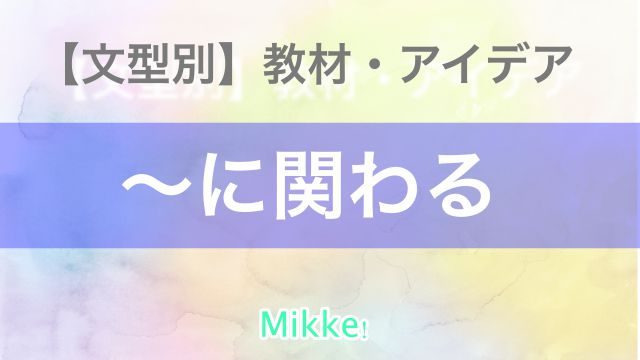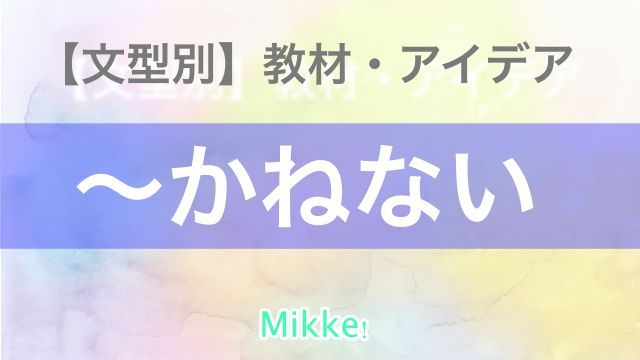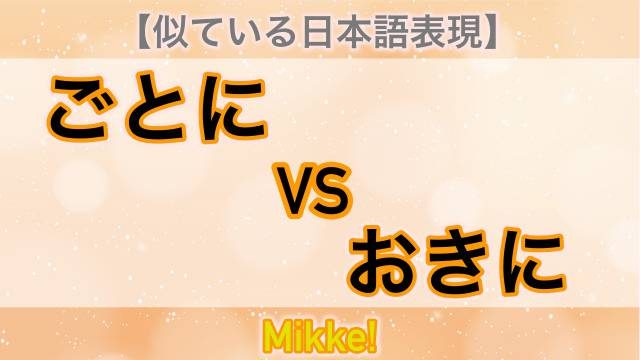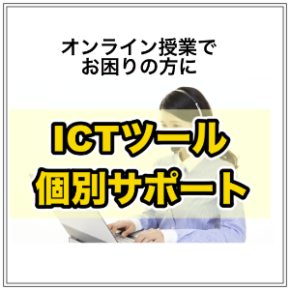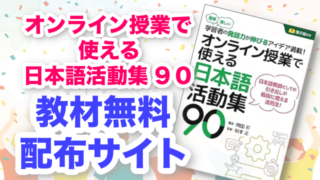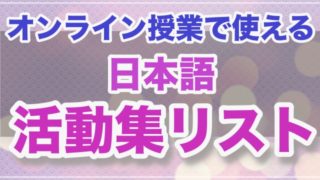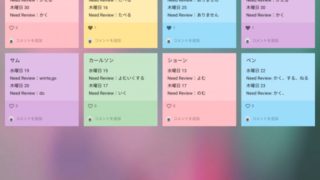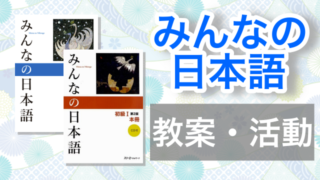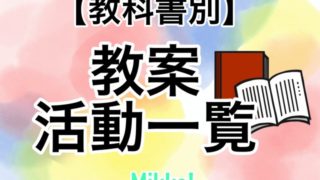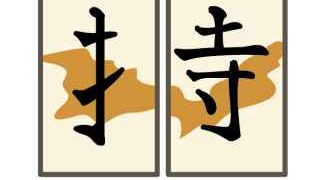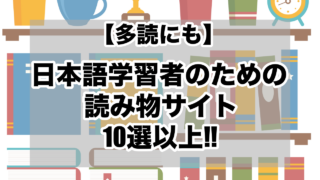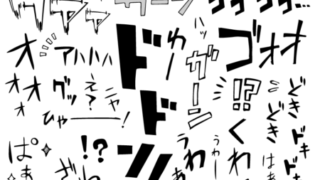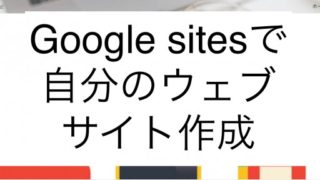このページでは、中級〜上級の日本語学習者向けに使える教材『めしあがれ-食文化で学ぶ上級日本語-』の使い方や活用アイディアを紹介しています。
尚、公開しているアイディアはMikke!独自のもので、くろしお出版さん公式のものではありません。
このページでは第10章の教案や練習アイディアを紹介しています。
「まずはこの教科書についてよく知りたい」という方は、こちらから各章の構成や内容をまずご覧ください。
ウォームアップ
T: 「みなさんは、小学生の時、お昼ご飯はどうしていましたか。」
S1:「たいてい家から食べ物を持って行きました。」
S2:「私は、学校のカフェテリアがあるので、そこで食べていました。」
T:「いいですね。日本の学校には、「給食」と呼ばれる文化があるんです。」
S2:「給食?」
T:「学校からお昼ご飯が出されるんですが、カフェテリアとは少し違います。」
S1:「あぁ、どこかで日本の給食について聞いたことがあります。」
T:「そうですか。日本のほとんどの小学校・中学校では、給食が出されます。この課では給食について読んでいきましょう。」
第1段落
単語の確認
事前に言葉の意味をチェックしてくる宿題を出しておきます。
意味は媒介語を書かせることを想定していますので、学習者の母語やレベルに応じて編集して使ってください。
『めしあがれ』第10章(第1段落)の宿題プリントをダウンロードする(準備中)
本文を読む
まずはクラス全体で本文を順番に一文ずつ読みます。
その後ペアになり、もう一度第一段落を読みます。
次に絵を見せながら、この段落のトピックについて理解を深めます。
■給食の例
「給食」とだけ言ってもイメージがわかない人がほとんどだと思いますので、写真を使っていくつか例を見せるといいでしょう。

余裕があれば、それぞれのメニューにどんな具材が使われているのか、話し合います。
1回の給食の中でも色々な具材が使われていることに気づくことができると、いいのではないでしょうか。
■献立表
「献立表」というコンセプトがわからない学習者もいるので、実際の献立表を見せて
- どのようなメニューがあるのか
- メニュー以外にも、どんな内容が盛り込まれているのか
- 他に気づいた点があるか
などについて話し合う。
■食育
下記のような写真をもとに、「食育」について考えます。
「給食は食育の一環。給食をクラスメイトや先生と一緒に同じものを食べることは、どんな食育につながると思う?」など問いかけながら話し合ってみましょう。
文型(例文・練習)
〜を指す(refer to)
次の言葉が何を指しているか、考えてみましょう。
- プレハブ
- チューハイ
- アラサー
- リスケ
<解答例>
- プレハブ小屋、という建築現場などで簡単に組み立てることができる建物のことを指しています。(プレハブ=prefab)
- お酒をソフトドリンクで割った、アルコールが低い飲み物のことを指します
- Around thirtyの略で30歳前後の年齢のことを指します。
- Rescheduleの略でスケジュールを再調整することを指します。
〜上(じょう)
適切な単語を選んでください。
【選択肢】教育上、健康上、理論上、法律上、想像上
- このアイディアは、_____は可能だが、実現は難しいかもしれない。
- お菓子を食べすぎると、_____の問題が出ることもあるだろう。
- 子供に暴力的なテレビを見せるのは______良くないと考えられている。
- 竜は_____の生き物で、実在しない。
- 18歳未満の人は、______お酒を飲んではいけないことになっています。
<解答例>
- 理論上
- 健康上
- 教育上
- 想像上
- 法律上
Nounとして
- 寿司は、_______としてよく知られている。
- 私の弟は、_____として働いている。
- スマホは、電話としてだけでなく、_____としても使える。
- 田中さんはチームの______として、仕事をがんばっている。
<解答例>
- 伝統的な和食
- シェフ
- カメラや地図
- 一員/リーダー/マネージャー
内容理解
- ( )給食のお金は全て県が出してくれる。
- ( )給食には安全性を考慮し、生物は出ない。
- ( )教室で給食をみな一緒に食べることも、教育の一環として考えられている。
<解答例>
- X・・・各家庭から1食200円〜300円で支給される
- ○・・・刺身などの生物は出ない
- ○・・・教員も一緒に食べる。
第2〜4段落
単語の確認
事前に言葉の意味をチェックしてくる宿題を出しておきます。
意味は媒介語を書かせることを想定していますので、学習者の母語やレベルに応じて編集して使ってください。
『めしあがれ』第10章(第2段落〜第4段落)の宿題プリントをダウンロードする(準備中)
本文を読む
まずはクラス全体で本文を順番に一文ずつ読みます。
その後ペアになり、もう一度第一段落を読みます。
次に絵やウェブサイトを見せながら、この段落のトピックについて理解を深めます。
第2段落
■食糧事情が悪かったとは?
当時、物資が不足していったために多くの食料品や家庭用品が配給制になりました。家庭用の塩、お米などは切符を持っていく配給制になっていたことを、写真を見ながら話すといいでしょう。
▪️食糧自給率について
お米が不足していたところから、近年の食料自給率について触れるのもいいでしょう。
第3段落
▪️多様化した給食の献立
ウェブサイトを見ながら、世界をテーマにした給食について学びます。
▪️和洋中とは?
和食、洋食、中華をまとめた言葉であることは理解できると思いますが、実際にそれぞれどんな料理があるのか、簡単に見ていきます。



Geniallyのリンクを渡しておき、各自でイラストをクリックしながら名前を見てもらうようにするアイディアもあります。
「食べたことがある料理、聞いたことがある料理がありますか?」など、問いかけながら見てみましょう。
▪️地産地消

自分たちが育てたり、課外学習で収穫体験をしたりした食物が給食に使われ、食べることができます。これらの活動も食育の一環に強く関わっていることを伝えます。
事例スライド2枚目の「①玉村町学校給食センター」の事例が完結でわかりやすいです。写真を一緒に見つつ、「どんな食べ物で何をしているのか」を引き出しながら地産地消の考え方について触れる機会を設けます。
第4段落
▪️栄養を考えた献立
文科省のウェブサイトに、学校給食の栄養のバランスの指標となるグラフがあります。第2段落で見せた学校給食の献立表と栄養バランスの表を照らし合わせながら、栄養が偏らないような工夫がされていることに触れます。
文型(例文・練習)
〜的(2回目)
積極的、健康的、栄養的、味覚的、基本的、視覚的
- ______な食生活を送るために、給食ではバランスの取れたメニューが考えられています。
- 彼女は_______に色々なボランティアに参加している。
- このドレッシングの_______なポイントは、後味の爽やかさだ。
- 野菜が苦手な子どもでも食べやすいように、色合いなど______にも配慮された盛り付けがされています。
- 成長期の子どもには、_______に優れた食事が必要だ。
- _____に給食ではみんな同じ量を食べますが、おかわりをすることもできます。
<解答例>
- 健康的
- 積極的
- 味覚的
- 視覚的
- 栄養的
- 基本的
〜化(2回目)
次の定義にあてはまる言葉を選びましょう。
単純化、一般化、欧米化、効率化、多様化、機械化
- 一般に広く知れ渡るようになること
- 西洋風に変わっていくこと
- 種類が1つではなく様々になること
- 手作業ではなく機械がたくさん使われるようになること
- 作業がシンプルになること
- 無駄な作業が省かれ、よりスムーズになること
<解答例>
- 一般化
- 欧米化
- 多様化
- 機械化
- 単純化
- 効率化
アウトプットしてみよう
自分の国の食料自給率を調べてみましょう。
- どの食品の自給率が多いですか。少ないですか。
- 意外だった食品がありますか。
- 他の国と比べてどうですか。
第5〜7段落
単語の確認
事前に言葉の意味をチェックしてくる宿題を出しておきます。
意味は媒介語を書かせることを想定していますので、学習者の母語やレベルに応じて編集して使ってください。
『めしあがれ』第10章(第5段落〜第7段落)の宿題プリントをダウンロードする(準備中)
本文を読む
まずはクラス全体で本文を順番に一文ずつ読みます。
その後ペアになり、もう一度第一段落を読みます。
次に絵やウェブサイトを見せながら、理解を深めます。
▪️学校の時間割
日本の小学校や中学校では「1時間目、2時間目」という呼び方をしており、時間はしっかりと区切られています。たいてい間に5分〜10分の休みがあり、4時間が終わると長めの昼休みになります。
文型(例文・練習)
〜たて
当てられた言葉を適切な形に変えて、文を作成しましょう。
- 焼く:このパン、まだあたたかい!きっと( )ですね。
- 炊く:わあ、このごはん、ピカピカでおいしそう。( )かな?
- いれる:コーヒーはやっぱり( )が一番おいしいですね。
- 取る:今日のおすしは、( )のえびを使っているそうですよ。
- 揚げる:天ぷらは、( )を食べるとサクサクで最高!
<解答例>
- 焼きたて
- 炊き立て
- 入れたて
- 取り立て
- 揚げたて
あるNoun
例文を読んで、意味を確認する。
- ある日、へんな人に会いました。
- ある国では、1年中雪がふります。
- ある先生がこんなことを言っていました。
- これは、ある友だちにもらったプレゼントです。
- あるところに、おじいさんとおばあさんがすんでいました。
直後に「近くにある」という言葉がありますが、この「ある」と、文型の「ある」とは別であることも確認しておくといいでしょう。
内容理解
- ( )給食センターは週に一回、出来立ての昼食を送ってくれる。
- ( )学校にはスタッフがいるので、学生はスタッフと一緒に料理をする。
- ( )配膳をする学生は白衣と呼ばれる衣服を着なければならない。
- ( )給食は当番を決めて、学生が順番に担当する。
- ( )日本全国の全ての中学校で、全く同じシステムで進められる。
<解答例>
- X・・・週に一回ではなく、毎日届けられる。
- X・・・学生は配膳のみで調理はしない。
- ○・・・正しい。
- ○・・・正しい。
- X・・・本文は「ある」中学校の話であり全ての中学校ではない。(中には教室ではなく給食室で食べる学校などもあります。ただしほとんどの学校が同じシステムであることは補足説明が必要です。)
第8〜10段落
単語の確認
事前に言葉の意味をチェックしてくる宿題を出しておきます。
意味は媒介語を書かせることを想定していますので、学習者の母語やレベルに応じて編集して使ってください。
『めしあがれ』第10章(第8段落〜第10段落)の宿題プリントをダウンロードする(準備中)
本文を読む
まずはクラス全体で本文を順番に一文ずつ読みます。
その後ペアになり、もう一度第一段落を読みます。
▪️食器返却の際のルール
片付けのラックでは、大きなキーチェーンに通してスプーンの束ができるように返却することが求められます。
他にも片付ける時に気を付けるべきことが学校によっては決められています。他にもどんなルールがあるか、考えてみましょう。
- ルールの例)
- 牛乳パックは飲み終わったら平らにつぶす
- お皿やお椀は同じ向きにそろえて返す
- ごみは燃えるごみ・牛乳パック・ストローなどに分別する
- 残った食べもの(パン・牛乳など)は決められた場所に返す
文型(例文・練習)
動詞語幹+終わる
- 本を( )終わってから、寝ました。
- ごはんを( )終わったら、デザートを食べましょう。
- 映画を( )終わってから、感想を話しました。
- 先生が説明を( )終わってから、テストを始めました。
<解答例>
- 読み
- 食べ
- 見
- し
内容理解
- 全員が給食を食べ終わったら、誰が前に出て挨拶をしますか。
- 食器を返却するラックには、どんな工夫がされていますか。
まとめ
自由会話
- 自分の国にも給食のような文化がありますか。
- もし自分で給食のメニューを作るなら、何を入れたいですか。
- アレルギーや宗教の食文化への対応は、どうしたらいいと思いますか。
- 自分の国に日本の給食スタイルを取り入れるとしたら、できそうですか?できなさそう?その理由は?
レシピを見る・読む
第10章のレシピは「カレーライス」です。
それから公式サイトにある動画を見たり、本書のレシピを読んで和食の作り方を学ぶことができます。
動画の使い方としては、
- ナレーションをアフレコさせる
- 大体の手順を後で日本語で説明できるようにメモをとらせる
- 途中の工程で独特なものがあれば、何のためにするのかを考えさせる
などがあります。
第10章だと、先生の方から次のような質問を促して考えてもらうこともできそうです。
- 人参や玉ねぎの切り方の名前を知っているか。(乱切り、くし切りなど)
- 切ったじゃがいもを水につける(さらす)のは、どうしてだと思うか。
- おたまで、何をすくっているのか。
『めしあがれ』のその他の章もご覧になりたい方は、下記リンクからどうぞ。